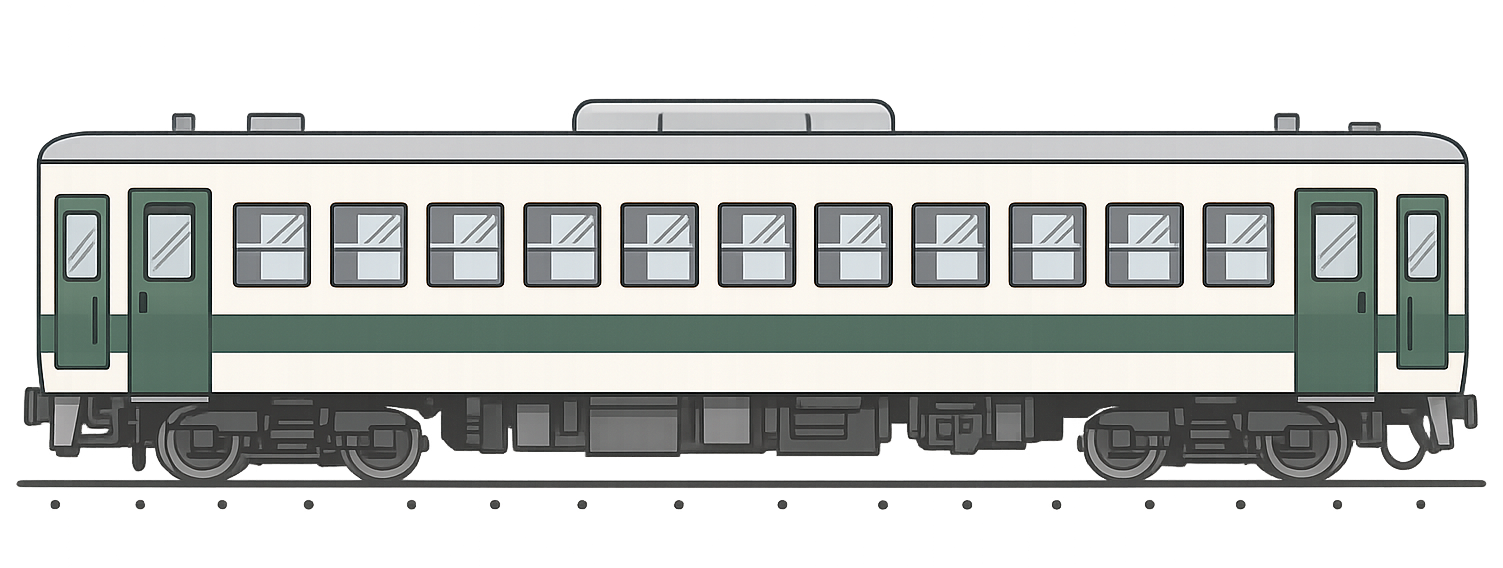思い出
(メッセージ本文
一関一高を、昭和33年(1957)に卒業した第57回生(310人)で、卒業後は、「一関一高三三会」と称しています。
三三会は、平成20.年(2008)卒業50年と古希の節目にあたり、記念誌「燦燦」を、平成21年(2009)5月に発刊しました。この「シゴハチロマン」は、その時に執筆したもので17年も前のものです。
私は陸中門崎駅から高校への通学と通勤に7年間利用しました。
当時は、一関へは大船渡線が唯一の足で、一ノ関駅に着くと東北本線の上り、下りと一緒になり人、人で騒々しい様子が浮かんできます。 まさに『栗駒 三陸 平泉 ここが起点の一関』です。
シゴハチは現在、一関市立図書館(平成26年7月開館)の地で保存されていますが、その経緯を紡ぐことも大事なことです。
シゴハチロマン
ジャッチャポッポ、ジャッチャポッポと黒い煙りと白い蒸気を吐きながら、走りつづけた蒸気機関車は、電化やディーゼル化など国鉄輸送の近代化によって廃車の運命を辿ったのは、昭和45年以降のことである。
一関文化センター東側に保存展示されているC58(シゴハチ)型は、民間の蒸気機関車を一関に残す会の呼びかけによって、国鉄盛岡鉄道管理局の無償貸与の理解を得て、スクラップから逃れ保護された。当初は、旧一関小学校の講堂跡地に保存されていたが、文化センターの建設に伴い、昭和57年7月に現在地に落ち着いている。
これは、次代の子どもたちに本物をプレゼントしたら百聞は一見にしかずで、絵や写真で語るよりも教育的効果が大きいし、機関車の労をねぎらうこともできるという一石二鳥を考えたからである。
シゴハチは、全部で427輌製造されたというが、この機関車は昭和13年12月27日、103番目として大阪で製造した「C58-103号」である。
各地の線路を運行し、昭和25年から一関機関区に配属され43年まで18年間大船渡線で活躍した。因みに、東北本線は、シゴハチより大きいD51(デゴイチ)型が、走っていた。
私は、このシゴハチに陸中門崎駅から通学と通勤でお世話になったので、見るたびに懐かしく、思いも多く、殊のほか愛着を感じる。
ヤマ汽車の急勾配を、黒い巨体を左右に振りながら「アンナサカ」「コンナサカ」と号令をかけながら動輪に鞭打って登りつめる。
男性らしい力強い音を響かせ鉄路を突き進む勇姿は、今でもはっきりと覚えている。
まさに、シゴハチに青春時代を引っぱって貰ったと言った方がいい。
シゴハチの保存移動は、一関機関区から駅前に出て、上の橋通りから広街の文化センターまで前長700メートルである。重量72トン。運搬方法は、機関区、保線区の国鉄技術者の設計により道路に順次レールを敷いての運搬。
作業は、昭和47年7月29日夜半から開始され市役所、国鉄、道路、企業、警察、消防など多くの関係者が出動した。
広街の曲がり角では、巨体が曲がり切れず機関車と炭車を切り離して廻れた。作業は翌30日まで、24時間を要した大移動だった。
スクラップの直前で救われ、国鉄の方々は俺たちの時代に、俺たちで運び残すことができたと、安堵と満足に喜びあったという。
保存後は、毎年5月8日に国鉄OBや現役JRの方が清掃、整備点検を行っている。このシゴハチも、今年満70年の古希を迎えた。
現役をしりぞきレールから消え、今ひっそりとしているが、一関の貴重な文化財として、大事に保存しなければならない。