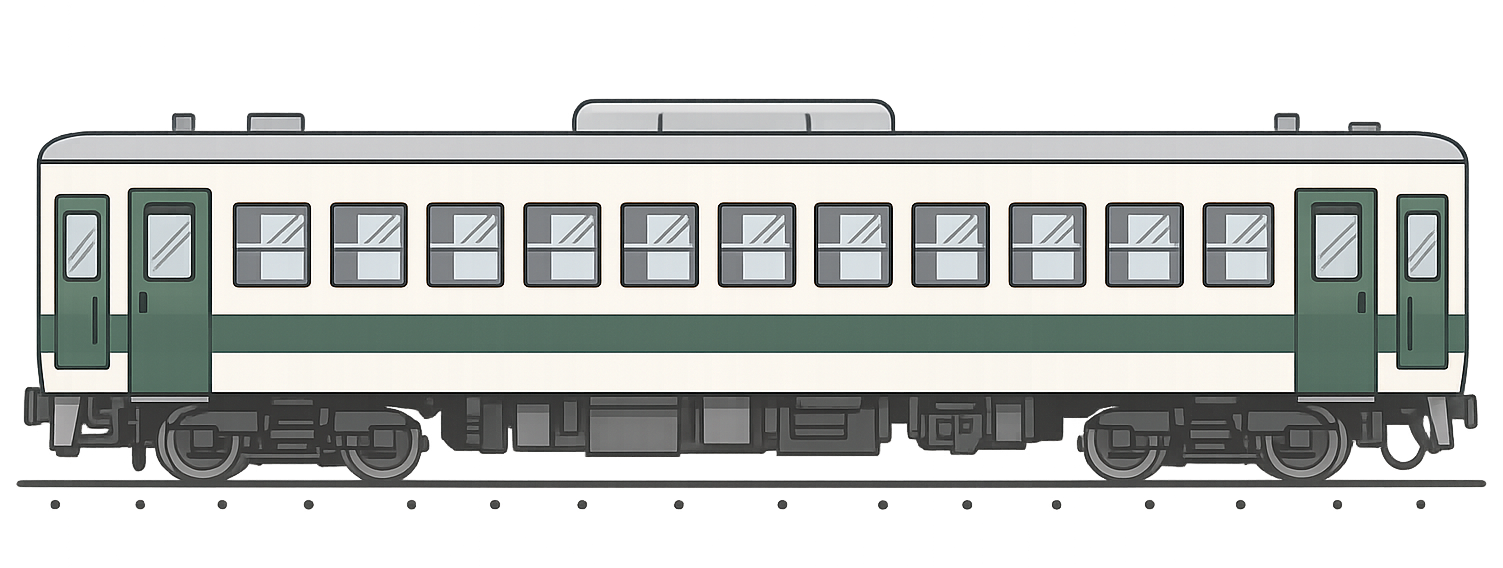大船渡線の歴史
一世紀にわたり、地域の発展と人々の暮らしを支えてきた大船渡線。
その軌跡をたどります。
| 駅名 | 一ノ関駅 | 真滝駅 | 陸中門崎駅 | 岩ノ下駅 | 陸中松川駅 | 猊鼻渓駅 | 柴宿駅 | 摺沢駅 | 千厩駅 | 小梨駅 | 矢越駅 | 折壁駅 | 新月駅 | 気仙沼駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開業年 | 1890年 | 1925年 | 1925年 | 1966年 | 1925年 | 1986年 | 1962年 | 1925年 | 1927年 | 1928年 | 1928年 | 1928年 | 1929年 | 1929年 |
| 2025年時点 開業周年 | 135周年 | 100周年 | 100周年 | 59周年 | 100周年 | 39周年 | 63周年 | 100周年 | 98周年 | 97周年 | 97周年 | 97周年 | 96周年 | 96周年 |
表は横にスクロールできます →

構想と「我田引鉄」の誕生
大船渡線の源流は、明治期の民間による「磐仙鉄道」計画に遡るが、資金難から二度にわたり挫折から始まりました。その後、国の事業として計画が進むと、ルート選定を巡り、摺沢を地盤とする政友会と千厩を地盤とする憲政会との間で激しい誘致合戦が繰り広げられました。政権の動向や選挙結果が直接的に計画に影響を与え、ルートは二転三転する事態に。その結果、一関から一度北へ大きく迂回し、南下して千厩に至るという極めて非効率なΩ状の線形が生まれました。これは政治家の地元への利益誘導「我田引鉄」の典型例とされ、後に「なべづる線」と揶揄される原因となりました。

難産の末の全線開通と地域の期待
政治的駆け引きの末にルートが定まると、大正14年(1925年)の一ノ関〜摺沢間を皮切りに、段階的に建設が進められました。昭和2年(1927年)には誘致運動の中心地であった千厩に、昭和4年(1929年)には三陸沿岸の主要都市である気仙沼に到達しました。その後も路線は北上を続け、昭和10年(1935年)、ついに終点の盛駅までが開業し、10年の歳月をかけて全線が開通しました。沿線住民は「悲願の鉄路開通」を熱狂的に歓迎し、鉄道を「文化の母」「産業の父」と見なして、地域の近代化と経済発展に大きな期待を寄せました。

戦後の発展と「ドラゴンレール」の愛称
全線開通後、大船渡線は地域の発展を支える大動脈としての役割を担いました。特に戦後の高度経済成長期には、昭和35年(1960年)に仙台直通の準急「むろね」が運行を開始するなど、優等列車が設定され都市間連絡機能が大幅に向上しました。昭和43年(1968年)には蒸気機関車が廃止される「無煙化」も達成され、近代化が進みました。そして平成4年(1992年)、かつて「なべづる線」と揶揄された特異な線形を、竜の姿に見立てた「ドラゴンレール大船渡線」の愛称が公募で決定しました。政治が生んだ負の遺産を、地域の魅力として再定義する象徴的な出来事でした。

東日本大震災と鉄路の断絶
平成23年(2011年)3月11日、東日本大震災が発生し、大船渡線は歴史上最大の岐路に立たされます。全線が不通となり、特に気仙沼駅から盛駅にかけての沿岸区間は、大津波によって壊滅的な被害を受けました。駅舎や路盤、橋梁の多くが流失し、「新線を建設するのに等しい状況」と描写されるほどでした。内陸部にあたる一ノ関〜気仙沼間が約3週間で運転を再開したのに対し、沿岸区間は復旧の目途が全く立たない状況に陥り、鉄路としての存続が根本から揺らぐ事態となりました。

BRTによる「仮復旧」という選択
甚大な被害を受けた沿岸区間に対し、沿線自治体は一貫して鉄路での復旧を強く要望しました。しかし、JR東日本は復旧に要する莫大な費用と期間、将来の利用客減少リスク、そして防災集団移転など新たなまちづくりとの整合性を考慮し、鉄路復旧は困難との立場を示しました。その代替案として提案されたのが、バス高速輸送システム(BRT)による「仮復旧」でした。最終的に地元自治体は、あくまで将来的な鉄路復旧の可能性を残す「仮」の措置であるとの前提でこの提案を受け入れ、決断を下しました。平成25年(2013年)、気仙沼〜盛間でBRTの運行が始まりました。

鉄路廃止と新たな地域交通モデルへの挑戦
BRTの運行開始後、専用道の整備や新駅設置などの改良が進められる一方、JR東日本と自治体の間で本復旧に関する協議が続けられました。最終的に、復旧コストやまちづくりとの整合性の観点から鉄路の再建は断念され、令和2年(2020年)4月1日、気仙沼〜盛間の鉄道事業は正式に廃止されました。これにより約85年間の鉄道の歴史に幕が下ろされ、BRTが恒久的な交通手段となりました。現在、BRTは自動運転技術の導入も視野に入れ、災害被災地の交通再生に留まらず、日本の地方が抱える公共交通問題の解決策を模索する先進的なモデルとして、新たな歴史を歩み始めています。